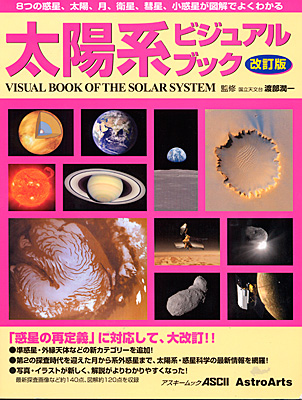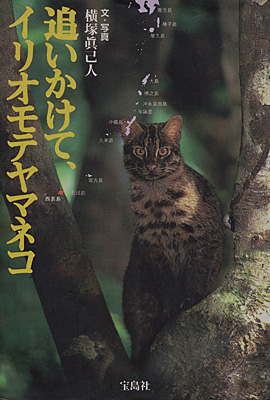| |
| |
| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |
| |
2011.10.29〜31(土〜月) いい物は高い
土〜日曜日はほぼ丸一日雨の予報。みんなで南九州へと旅行に行く予定になっていたのだが中止になった。
ただの旅行なら強行もありだろうが、テントで寝泊まりする場合、雨は辛い。
テントが新しければまだしも、それは僕が小学生くらいの時に父が買ったもので、当時としては超最高級品であったが、さすがに今となっては古くなり過ぎていて防水が怪しい。
代わりに博多の街へと買い物に行くことになり、モンベルショップで冬用の衣料品を買ってきた。
僕は、まず第一に、写真にお金をかけてきた。だから、着るものに関しては、常に不自由してきた。
着る物をそこそこ買えるようになったのは、せいぜいここ数年のことだ。
一番最初は、ある年にTシャツを買った。インターネットで安いTシャツを3枚買ったら、それが安価であるにも関わらず案外品質がよく、色違いで20枚くらい買った。
僕はいつも同じ服を着ているように見えるかもしれないが、同じものをたくさん持っているだけであり、実は毎日ちゃんと着替える。
翌年は、同じカッターシャツをまとめて買った。ユニクロの製品で、シーズンオフで安くなったものだった。
さらに翌年は、ジーパンを数枚買った。お尻が薄くなってパンツが透けて見えるズボンから、おさらばすることができた。
普段の生活に関して言えば、少々洗濯物をため込んでも、着物がなくて困るという事態にはならなくなった。
あとは、冬に野外で仕事をする際に着る物を充実させればいい。
ただ、冬に野外で着るものに関しては、それなりの品質のものでなければ寒くて撮影どころではない。
そして、買い物に行くといつも思い知らさせる。本当にいいものは、やはり高価だと。
これだ!と手に取ってみるものの、値札を見てあわてて元の場所に戻す。昨日だけで、それをいったい何度繰り返したことか。
衣料品などは、値段ごとに陳列してくれればいいのに、と思う。
街中をウロウロしたら、頭が痛くなった。
風邪をひいたというような肉体的なものなのか、都会の人ごみにやられてしまったというようなものかは不明。
これはいつものことであり、帰宅後1週間くらい経過すると、次第におさまってくる。
その症状を言葉で表すなら、気だるくて、追い詰められた感じがして、鬱の人が訴えるような状態に近い。
僕は日頃、機嫌が悪いとか、イライラするとか、妙に落ち込むというようなことが滅多にないタイプ。だから、気分にむらのある人のことがよく分からない面があるのだが、町を歩いた後だけは、多少理解できる。
僕の場合、落ち込むとするならば、お金の不安くらい。
それも、お金がないと直接的に苦しむよりは、稼がないかん!と焦り、焦れば焦るほど空回りして逆に無気力になるというようなもの。
受験生が、あまりのやることの多さに、気力がでないのに近い。
お金を持って、 贅沢をしたいわけではない。
いい本を作るためには、お金も必要になる。つまり、次の作品を作るための、運転資金が欲しいのだ。
|
| |
2011.10.27〜28(木〜金) う○こをしている間に



関門海峡を渡るヒヨドリの撮影には早朝がいい、と聞いたので、朝早くに出かけてみた。
前日の夜が遅かったこともあり、朝ギリギリまで寝てバタバタ出発したため、その日の体調を十分に確認するための時間が取れず、現場で腹具合が悪くなり、う○こをしたくなった。
キュルキュル泣くお腹をいたわりながら、小学校の時の友人の「のぐや」こと野口くんを思い出した。
みなで遊びに行った際にのぐやがう○こをしたくなり、草むらで済ませて葉っぱでお尻を拭いた出来事は、トムソーヤの冒険にかけて、ノグソーヤの冒険と名付けられた。
野口君は確か、お父さんが国鉄にお勤めで、鉄道のすぐ裏の住宅に住んでいたように記憶している。
野口君をはじめ、僕が小学生のころに好きだった友達は、高い確率で転校をしていった。富田君、奥田さん、畠山君、野口君・・・ みな、いつの間にかいなくなっていた。
ともあれ、知人の野村さんが傍にいたので、三脚に取りつけたレンズとカメラを放置して、藪のなかで野○ソを済ませてカメラの元に戻る直前、バシャッと大波が押し寄せてきて、望遠レンズ+カメラの上に降り注ぐのが見えたのには驚いた。
近所を大きな船が通ると、数分後に大波が押し寄せてくるのだ。
撮影機材が水しぶきに覆われると大変なことが起きたような気になるが、水滴が可動部にさえ入らなければいいのだから、冷静になること。
すると、急いで拭かなければならない個所は、それほど多くはない。
|
| |
2011.10.25〜26(火〜水) うまくなればいい
全293ページ。岩合光昭さんのページ(P7〜34)を読みたくて10年以上前に買った本だ。
「食っていくためには、うまくなればいい」
と書いてある。そして、自然写真の分野でほんとうにうまいのは、世界で10人くらいだと。
他に、236ページからの飯沢耕太郎さんの「僕が写真家になれなかった理由」も面白い。自身とこの本の中で取り上げられた岩合さん他の写真家とを比較し、プロの写真家には何が必要なのかを論じておられる。
僕のように、特に才能に恵まれているわけでも上手いわけではない者の場合、飯を食おうとすれば、悲しいかな市場のニーズを強く意識し、それに合わせざるを得ない。
一方で、ニーズに応えるだけでなく、新しい世界を切り開きたいとも思う。
だから、どこでニーズに応え、どこで新しい世界を切り開こうとするのかは、僕にとって大きな悩みであり、ここ数年は常にそのことで頭がいっぱいだと言える。
それをちょっと忘れたいなという気持ちも、近頃正直に言えばある。
悩んでいると受け止められると、違和感がある。
苦しみつつも一生懸命に写真を撮りつつ、一方で、たかが自然写真、遊びじゃねぇかと思う。その矛盾する気持ちを、心の中に当たり前に同居させることを、僕は重視している。
「水と地球の研究ノート/偕成社」は、本を作る段階で、学校教育の現場を意識するというようなやり方で、世間のニーズに応えようとした。
一方で撮影の段階では、とにかく自分が好きなものだけにカメラを向けた。スタジオでの写真は一枚もないし、思い入れがある場所で、撮りたいものだけを撮りたいように撮った。
本作りが終わってみると、自由に撮影したその余韻で、世のニーズに応えるために定番のシーンを撮影することやスタジオ撮影がひどく苦痛に感じられるようになった。
とにかく、腰が重たいのである。
この日記を長く読んでおられる方は、僕がこれまで、世間のニーズに応えることを、過剰なくらいに重視してきたことをご存知かと思う。
なぜ、それほどニーズに応えることにこだわったのかと言えば、僕は、本来そうしたことができにくいタイプなので、そうした自分を戒めてきたのだ。そして、そのたがが、外れたのかもしれない。
引き返すことはできないので、前に進むしかない。
ともあれ、世の需要にこたえることと、新しい世界を切り開くことの両立は、僕にとって相変わらずむづかしい。
仕事って、厳しいなぁ。
|
| |
2011.10.22〜24(土〜月) 男と女


上がアカイエカのオス、下がメス。
雌雄で形態が異なるのはもちろん、性質に関しても、スタジオでいろいろと触ってみるとかなり異なる。生き物のオスとメスとは、時としてほとんど別の生き物だと言ってもいいくらいに違う。
人も、同じ種類の生き物のだからと言って男女が同じだと考えるのは、思い込みである可能性もある。自然を眺めてみると、そんなことがチラッとわかる。
(撮影テクニックの話)
さて、自然写真の世界は、工夫のるつぼ。人が開発した、さまざまな手法が存在する。
僕は、一通りのことを、やってみることにしている。
だが試してはみるものの、そこで撮影した写真は、おそらく公にすることはないだろうなと思いながら撮影している写真もある。
たとえば、虫の目レンズと呼ばれる特殊な効果が得られるレンズで撮影した写真。
それから、深度合成と呼ばれるテクニック。
別にそれらの手法が嫌いなわけではなく、むしろ面白いなと思うし、さらにそれを開発した人に対しては、興味と尊敬の思いが込み上げてくる。
だが、それらはいずれも完成された表現であり、それを真似、自分の作品として発表するのは、プロとしてはないと考えている。一部のカメラに搭載されているアートフィルターなどというのも、同様に思う。
一方で、赤外線センサーを使用した自動撮影などは、僕もたまに使用する。
こちらは、表現ではなくて、写真を撮るための技術である。
自分なりに、真似てもいい部分と真似てはならない部分とがある。
(お知らせ)
北九州市若松区響灘グリーンパークにて、写真展を開催中です。
期間 10.月20日(木)〜10月25日(火)9:00〜17:00 火曜日は休館日
入園料 100円
駐車料 300円
内容 野村芳宏 西本晋也 武田晋一による3人展
|
| |
2011.10.21(金) 縁
ソフトバンクの携帯電話を解約するために、ショップへ。
同社のホワイトプランに加入すると、ソフトバンクの電話どうしの通話が、ある時間帯無料になる。それを利用すれば、仕事の打ち合わせなどに都合が良さそうだという理由で持っていたのだが、近年、年を追うごとに電話が嫌いになってきて、ついに解約することになった。
電話に限らず、僕は繋がりたいとかさみしいと感じることが滅多にないタイプであり、幼い頃から一人になりたい傾向が強かったようだ。
だがそんな僕だからこそ、人との出会いや縁はありがたい。
放っておくと、ひたすらに自分が好きなことだけに打ち込んでしまうところに、誰かが新しい何かを持ってきてくれる。
数年前、直方の谷尾美術館で、「筑豊アートシーン」というイベントに参加させてもらったのだが、アートを志す人たちの世界を、チラッとではあるが、見ることができた。だからと言ってアートが分かるようになるわけではないが、それをきっかけに、次第に興味が湧いてきて、ヘェというくらいには、楽しく感じられるようになってきた。
さて、以前一緒に仕事をしたことがある方から、
「私が編集した本なんですよ。」
といただいたい本。
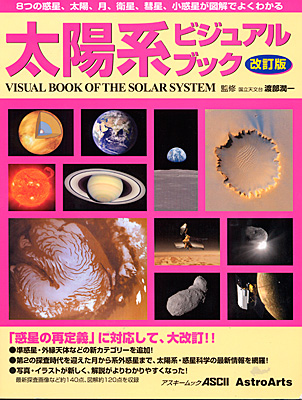
こちらは、幾つかの太陽系の星について、1つずつ詳しく、そのプロフィールを紹介したもの。

こちらは、宇宙の面白い小話を集めたもの。
共に、学校の図書館においてあったり、先生が授業の準備をする際などに見るのに適した本だと感じた。
実は僕は、自然の中でも天文には興味を持ったことがなかった。
興味を感じないというよりは、あまりにスケールが大き過ぎて、考えが及ばないといった方がいいのかもしれない。
ところが、私が編集した本なんですよ、と渡されると、面白くなってくる。
僕は、一人になりたい人間なので、名刺を配りまくったり、縁を頼りに直接的に仕事を得たいとはあまり思わないのだが、何かの縁で自分が新しいものを知り、それをきっかけに自分が変わり、その変わった自分が世間から必要とされるというような形で、仕事ができたらなと思う。
(お知らせ)
北九州市若松区響灘グリーンパークにて、写真展を開催中です。
期間 10.月20日(木)〜10月25日(火)9:00〜17:00 火曜日は休館日
入園料 100円
駐車料 300円
内容 野村芳宏 西本晋也 武田晋一による3人展
|
| |
2011.10.20(木) お知らせ

(お知らせ)
北九州市若松区響灘グリーンパークにて、写真展を開催中です。
期間 10.月20日(木)〜10月25日(火)9:00〜17:00 火曜日は休館日
入園料 100円
駐車料 300円
内容 野村芳宏 西本晋也 武田晋一による3人展
|
| |
2011.10.19(水) 最高の一冊
講演で生き物の話をすればいいのなら、いつも考えていることであるし、僕にとってそれほど大変なことではない。ところが、学校の先生方の前で話をするとなると、僕の仕事と教育との接点を見出さなければならないから、準備に大変に時間がかかる。
ただ、そこで頭の中を整理し一度言葉にしてみることには、大変に意義があったと思う。
学校は、集団生活をする上でのブレーキの踏み方を教わる場所だと言える。ブレーキの利きが悪い人間は、組織の中では危なすぎる。
一方で、自然写真のような仕事、つまり組織に属さず、自らの道を自分でつけていくようなタイプの仕事を選択した場合は、ブレーキよりもアクセルを踏み込めることが大切になる。
なぜなら、僕らの世界はそれが好きな人の集まりであり、一般的な感覚でいう『やる気がある』が当たり前であり、最低限のラインであって、その上にどれだけ積み重ねることができるかの勝負だからだ。
自然科学の研究者などにも言えることだろうが、ある意味、変態でなければならない面がある。
ところが、日本の社会はブレーキだらけであり、アクセルの踏み方を学べる場所はほとんどない。
そこで僕は、アクセルを踏むというのは、どんなことなのか、自分なりに話をしてみた。
話を終えて帰宅をしてみたら、一冊の本が頭に浮かんだ。
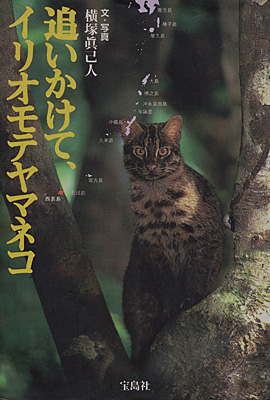
追いかけて、イリオモテヤマネコ / 横塚眞己人 / 宝島社
イリオモテヤマネコを撮影するために、西表島に移住した横塚眞己人さんの読み物。
この中で横塚さんは、法律を破ってしまったことを告白しておられる。どうしてもイリオモテヤマネコを撮影したくて、天然記念物には禁じられている餌付けをやってしまったのだ。
ところがある日、自分が置いた餌ではない、別の餌が置かれていることに気付き、どこのどいつだと犯人を捜し、それと思しき人物を見つけ出す。
同時に自らを見つめ、自分の餌付けをやめ、正々堂々撮影しようじゃないかと戒め、当初目標として掲げたイリオモテヤマネコの親子の撮影を成功させる。
法を犯すことがいいことだとは思わないが、僕は、今日本の社会や教育に足りないのは、そんな部分ではないかと思う。失敗したり、間違いをおかしながらも、自分を見つめ、変わっていく。
アクセルを踏むというのは、基本的にそんなことだと思う。
インターネットが普及して以来、その間違えを目を皿のようにして探し、「こんな悪い奴がいた」と報告することを生きがいのようにしている人がいて、そんなブログやツイートが山のようにあることが分かった。
僕らのような世界だってブレーキを否定するつもりはない。が、ブレーキさえ踏んでおけばいいというのは大間違いではなかろうか。
「餌付けなどという方法を使うのは、自分が写真さえ撮れればいいと考えていて、生き物に対する愛情がない人だ。」
と主張する方がおられる。
もちろん、そんな人もいると思う。ただ 楽に 写真を撮りたいというだけの人も。
だが人という生き物は、そんなに簡単な存在ではない。その生き物が死ぬほど好きだから、どうしても撮影したくて、いろいろな手を講じるのも人間。むしろ、
「餌付けなどという方法を使うのは、自分が写真さえ撮れればいいと考えていて、生き物に対する愛情がない人だ。」
と主張する人が、どこまでも何かを好きになった人の気持ちを理解できないだけという側面もあるだろう。嘘だと思うのなら、この本を読んで、横塚さんと同じことが自分にできるかどうか、考えてみたらいい。
或いは、恋愛を考えてみたらよくわかる。相手を好きで好きでたまらなくなるというのは、理性を飛び越えていくことだと言える。
「相手の負担にならないように・・・」
などといって理性で自分を制御できている間は、そこまで相手には惚れ込んでいないのだと言える。
『追いかけて、イリオモテヤマネコ』 は、自然写真家が書いた読み物の中では、最高の一冊だと思う。
ともあれ、自分のボロいところ、後ろめたいところをさらけ出せるのは、スゴイなと感じる。横塚さんは、写真の技術も含めて、僕が現役最高の一人だと思う自然写真家だ。
おそらく、下のリンクは、文庫化したものだと思う。
|
| |
2011.10.18(火) 新製品
僕は、小学生の頃に問題児だった。
問題児という言葉は、差別的であるというような理由で不適切である可能性もあるが、当時、そう言われていたので、そのままの言葉を使おうと思う。
だから、学校の先生を目の前にすると、後ろめたくて、どうも落ち着かなくなる。
そんな僕が、今年は何度も先生方の前に立ち、自然や本作りや写真の仕事について話をした。
かっこつけずに、最初に自分が問題児だったことを告白してしまえば、随分気が楽になることがわかった。
それどころか、僕の当時の状況を、目を輝かせて聞いてくださる先生がたくさんおられることには、逆に驚かされた。
ともあれ、今年最後の話が終わり、気が楽になった。
10月は、幾つか新しいカメラが発表されるうわさがあり、その中には僕が今主に使用しているニコンのカメラも含まれているが、気が楽になったとたんに、待ち遠しくてたまらなくなった。
噂通りのものが発売されるなら、使ってみたい気持ちはある。
知人が務めるカメラ屋さんで、予約をすることになるだろう。N君たのんだよ!
いや、先に値段を確認する必要があった。
(撮影機材の話)
すでに発表済みのカメラでは、ニコン1は、少々気になる存在だ。
僕の場合、一般的な撮影の他に、水中、洞窟、スタジオ、センサーを使用した撮影など、大半の自然写真家よりも撮影の幅が広い。
すると、より多くの機材が必要になりお金もかかるが、その場合に、1つの機材が2つ以上の役割を果たしてくれると大変にありがたい。
ニコン1の場合は、すでに所有しているニコンの望遠レンズと組み合わせれば、遠くの野鳥の撮影などには威力を発揮するに違いない。
そしてあと1つ、秒60コマの連写。
2つの用途に使えそうなのでは、欲しいなと思うのだが、秒60コマの連写には、どうも制限があるようなのでちょっと迷う。
また、浅い場所での水中撮影用に、、オリンパスのマイクロフォーサーズのカメラにも興味があるが、新製品はカメラを防水ケースに入れた場合に、ケースの外からの操作がやりにくいような作りになっているのが気になり、保留にしてある。
|
| |
2011.10.16〜17(日〜月) 公
よくぞ、こんなに!というほど、雑務をため込んでしまった。
封も切っていない封書。目も通さずに積んであるハガキ。未整理の領収書の山。
2週続けて、大の苦手である人前での話があり、他のことが何も手につかなくなっていた。
僕に連絡がある場合は、なるべくメールにしてもらえるとありがたい。封書やハガキは、こうして目が届きにくくなる場合がある。
主に、小学校と中学校の先生方の前で話をした。
不登校の子供たちにかかわっておられる方から、
「名刺をもらえませんか?」
と求められたのだが、僕には名刺を持ち歩く習慣がなく、困った。
しかし形だけ探してみよう、とパソコンを入れて持って行ったケースを探ってみたら、思いがけず手帳がでてきて、その手帳の中を、どうせ見つからないだろうなと思いつつ探してみたら、なんと名刺が出てきた。
僕は、不登校になった経験はない。が、それは、僕の時代に不登校という発想がメジャーではなかったからであり、今なら、そうなった可能性も大いにあると思う。それゆえに、何かできないかな、という気持ちがはある。
発信者にとって、何を発信するのかは非常に重要なことだが、どんなやり方で発信をするのかも、それなりに大きなことだと思う。
本なのか、WEBなのか、講演なのか。
僕はこうしてインターネットを使って発信をしており、WEBの良さや威力はそれなりに分かっているつもりだが、一方で所詮WEBだな、と思う部分もある。WEBは、どんなに気張っても、やっぱり気楽なのだ。
誰でも発信できるということは、逆に言えば、誰でもいいという側面も付きまとう。
その点、出版(自費出版を除く)は、そうはいかない。
だから本は権威であり、それゆえに本作りは疲れるが、その圧力の中で何かをすることに意味がある。
講演の場合は、その場がどんな場なのかによって、大きく違ってくる。
写真教室のような場は、気が楽で、リラックスできる。
逆に、教育の現場などというのは、大変にプレッシャーがかかる。
僕は高校の理科の教員の免許を持っていて、高校生に理科を教えたことがある。おそらく1500時間くらいは授業をしているはずだが、相手が高校生なら、義務教育ではないので、ずいぶん気が楽になる。
しかし、小〜中学校の義務教育の場は、日本人全員に関係する場であり、重みが違う。
『公』という言葉があるが、まさに『公』の中の『公』なのだ。
インターネットの掲示板などを眺めていると、その管理人などに対して、
「掲示板は公の場であるから、それなりの対応をしろ」
といったことを要求する方がおられる。
確かに、インターネットは世界中につながっており誰でも見れるとするならば、公であるとも言えるが、僕はその考えは取らない。ある一個人の意思でどうにもできる場であり、プライベートな場だと考える。
公が上で、プライベートが下であるとは思わないのだが、公って重たいなぁとしみじみ感じた。
質疑応答の時間に、福岡県内でも自然豊かな場所にある学校の先生が、
「実は私、生き物が苦手で、子供たちに生き物を見せられて、これ名前なになどと聞かれると・・・」
と話をしてくださったのだが、大変に面白かった。
その先生は、別の機会にも、僕の話を聞いてくださったのだそうだ。
|
| |
2011.10.13〜15(木〜土) 鈍感力
講演の会場に行ってみたら、人影がない。おかしいなぁと思いつつ、しばらく待ってみても変化なし。
そこで、書類をよく見てみたら、話をするのは明日のことだった。
主に学校の先生が集まる場で話をするのだが、大きなイベントらしくて日程が2日に渡っており、パンフレットに記されてる15〜16日と文字の15日という数字を計画表の中に書き込んでしまったことによる失敗だった。
ああ、情けない。
僕はうっかりが多いタイプなので、そんなことは十分に起こり得ることは自覚しているつもりだ。
だから、なるべくなら人と約束をしたくない。
人と何かをすること自体がいやなのではなくて、それに伴う自分のうっかりに怯え、精神的に疲れて果ててしまうのだ。
「鈍感力」などという言葉が、ちらっと頭に思い浮かぶ。
とにかく、明日。
気楽ではない公式な場で話をすることは、やはり大変に意義があることだと感じる。
うかつなことや辻褄が合わないことを言わないように、自分をしっかり見つめなければならない。
そのプレッシャーが、大嫌いでもあり、ありがたくもある。そのプレッシャーががなければ、気付けないことがある。
|
| |
2011.10.12(水) 赤点
15日の土曜日は、また学校の先生方の前で話をすることになっている。
質疑の時間も含めて2時間くらい。今回は、確か300人くらいお越しになるのだったと思う。
その後も、人前に立つ機会が年内にまだ残っているけどれども、そちらは写真の話であり、実技中心なので気が楽だ。
人前に出るのが大の苦手の僕が、今年は講演の連続だけれども、次の15日でついに解放される。
本来なら、その準備がとっくの昔に終わっていなければならないのだが、いまだ苦戦中。
元々は、数日間に渡って午前中に話の準備をして、午後からは蚊の撮影をしながら終わらせるつもりでいたのが、話の準備が進まないものだから蚊の撮影を先延ばしにせざるを得なくなる。
一番肝心な撮影を取りやめにするのだから、自己嫌悪に陥りがちになる。
さらに数日が経過して、それでも話の準備が整わないと、今度は蚊の撮影との両立どころか、講演の準備そのものが間に合わなくなるのではないか?という不安が込み上げてきて、間に合いさえすればいいという気持ちになる。
学生時代が思い出される。
最初、次のテストは絶対にいい点取るぞと固く決意するものの、やがていい点をあきらめ人並みでいいと考え、最後は赤点でなければ十分と思う。
ならば、日記を更新している場合ではないだろうとも思うが、撮影や何かの作業と違って、話の準備は、忙しというよりは何話そうか?と悩み、それが思いつかないだけで、決して手が空いてないわけではないのだ。
1つ言えることは、どうも僕にはその手の作業は不向きだと思えること。
ただ、向き・不向きや何を取り、何を捨てるかは、まずはやってみて、一度はそれなりの評価を得てから判断したい。
|
| |
2011.10.11(火) 勉強
ちょっと訳あって、高校生の試験勉強にお付き合い。本来は早寝で、できれば9時か10時には寝たい僕が、連日1時〜2時の夜更かし。
そんなことをしている暇はない、という気持ちがないわけではないが、自然写真家の中には家庭を持ち、撮影の仕事と同時に子育てをしておられる方も多数おられ、そうした方々に比べれば僕などはズルいといってもいいくらいに暇な方であろう。だから、何か自ら負担を背負い込むくらいで、ようやくみなさんと対等になると考えることにしている。
「高校生の頃はあんなに難しく感じられた勉強が、今なら簡単やん」
などと大人になってから何度か感じた機会があったが、実際に教科書を開き、高校生と一緒に試験勉強をしてみると、それは気のせいだったことを思い知らされる。
気のせい、というのは言い過ぎかもしれない。
確かにある部分を見れば、昔難しかったことが、今なら簡単にわかるというケースは多々ある。
だが全体としてみれば、学校の勉強はとにかく量が多くて、やっぱり甘くない。
むしろ、自分が受験を乗り越えてきたことが、よくぞ、あんな厄介なことができたな、と今度は信じられなくなる。
僕が学生の頃、武田家では大学に行くと言えば国立に行くことであり、私立という選択肢はないように思えた。
実際には、妹も弟も私立の学校にいったことを思うと、それは僕の思い過ごしだったのだろうけど、思い込みであるにせよ、国立しか許されないという状況は、5教科7科目(国語、数学、英語、生物、世界史、理科Ⅰ、現代社会)を受験することであり、僕のような偏ったタイプの人間には、非常に酷な話であった。
特に、国語の全200点のうちの100点を占める古典と漢文が苦しかった。
授業はさっぱり理解できず、古典も漢文も、毎回ほぼ0点だったから、これは大変に大きなハンディだった。
なんであんなに不親切な説明の授業を、先生は繰り広げるのだろう?分かるわけがない、という思いがいつもあった。
そしてその答えがわかったのは、つい最近のことだ。
うちに起こしになったある編集者(国語の教員の資格をもっておられる)が、
「古典とか漢文って、勉強しなくても読めばだいたいわかるでしょう。」
とおっしゃったのだった。
ああ、そうなのか。得意な人にとっては、そんなものなんだ。
勉強が難しかったはずだ。
|
| |
2011.10.10(月) 更新のお知らせ
今月の水辺を更新しました。
|
| |
2011.10.8〜9(土〜日) 教育とは
『水と地球の研究ノート/偕成社』は、小学校の理科の教育現場を意識しながら作った。
理科の本なのだから、
「私は、・・・」
と自分の感情について語るのではなくて、
「自然は、・・・」
と語りかけた。
出版後は、幾つかの地区の先生方の集会に参加させてもらい、本を紹介させてもらった。
ただ、人前で話をするのは大の苦手。その苦手を何度もこなすのだから、春に本が完成してからもう2〜3年はたっているかのような錯覚に陥りそうになる。その分撮影がおろそかになり、やぶ蛇だったかなぁという思いも、正直あった。
毎回同じ話をする、という手もあるが、そうではなく、毎回一から話を組み立て直した。
それゆえに準備には、毎回思いの他多くの時間を要した。
話をしながら聴衆の反応を見て、どんな話をした時に先生方が頷いたり目をギラギラさせてくださるのかを注意深く観察し、それを元に、次に話をする際には話の中身を考え直す。
昨日も、ある地区の先生方の集まりに参加させてもらった。
そんなことを繰り返すうちに、僕は、 『水と地球の研究ノート/偕成社』 で、「自然は、・・・」と話しかけたが、教育ってやっぱり主役は人なんだなぁと感じるようになってきた。
いやいや、そんなことはもしかしたら改めて書く間でもなく、当たり前のことなのかもしれない。
自分自身のことを考えてみても、例えば大学時代の恩師の言葉で思い出すのは、生物学の話や自然の話ではなくて、「人間とは何か?」という話だ。
僕は近頃、特に原発事故以降、恩師のある言葉を頻繁に思い出す。
「人のすることは、決して理屈通りにいきませんよ。右に触れたり、その反動で今度は左に触れたりすることを繰り返しながら、少しずつ少しずつ前に進んでいくものなんです。特に、大切なことであればあるほど、そうなんです。」
という言葉を。
実験をするよりも理屈をこね、手を動かそうとしない僕ら学生に対して恩師が語ったその言葉を今でも思い出すのに、その際のテーマだった実験の中身については、今や一切思い出すことができない。
|
| |
2011.10.7(金) 痛み
庭仕事というか、土方というのか、二日間、労働をしたら腰が痛くなった。
腰に痛みを感じたのは、生まれてはじめてのこと。経験のない痛みだったし、油断をしたら慢性化させて面倒なことになりそうだと思えたので、その後、何をするにしても無理をし過ぎないように細心の注意を払う。
この年になるまで腰痛というやつを経験しなかったのは、おそらく父の影響だろうと思う。父は、僕らがへっぴり腰で何か作業をしていると、
「構えが悪い!」
とすぐに拳骨を飛ばした。
おかげで僕は、まずは腰をしっかり据え、じっくりと作業をする習慣がついた。
すばらしい教育ですね、という方もおられるが、そうした教育に加え、父はイライラ不機嫌になりやすく、一緒にどこかに行くと必ず2〜3度は叩かれるとあって、僕ら兄弟は父とは一緒に出掛けたがらなくなった。とにかく、楽しむことが下手な人なのである。
肩なら、6〜7年前にひどく痛めたことがあった。
水温10度前後での渓谷で長時間の水中撮影を終え、体がカチカチ、クタクタになったのちに横になり、しばらく眠って目を覚ましたら、ひどい痛みに見舞われていた。
いつもなら、そんな水温の場合はドライスーツといって防水の衣服を着用するのだが、その日はウエットスーツを選んだ。撮影現場まで山道をかなり歩かなければならず、ドライスーツを使うと荷物が重たくなってしまうからだが、やはりドライスーツを使うべきだった。
さらに、撮影終了後は、体が十分に温まるまでストレッチをするなど、アフターケアーを十分にすべきだったと思う。
横になっている時以外は、どんな時にも耐えがたい痛みがあった。
用事があり、痛みを抱えたまま上京し、夜、昆虫写真家の海野先生の事務所によってみたら、海野先生が昔よく行ったバーがあるから、行ってみようかとさそってくださった。
「まだあるかな?あ、ある。もう10年以上行ってないからなぁ。」
とドアを開けたら、おかまの店主が、
「あっ海野さん。」
とまるでつい昨日にでもあったばかりであるかのように、迎え入れてくれた。
田舎者の僕には見たことがない空間だったし、写真の話もとても楽しかったのだが、その分、すべてを台無しにする肩の痛みが、より一層恨めしかった。
無事これ名馬、としみじみ思った。
ともあれ、時には、悪天候や厳しい気象条件の中で踏ん張らなければならない仕事であるだけに体は資本であるし、体調管理にはより一層気を配りたい。
|
| |
2011.10.6(木) 続・食べ物の話〜原発の話
日本で野生化した外国の生き物中には、ペットのように、食糧以外の目的で輸入されたものも多数存在する。
そしてそれらの外来の生き物に関して、野に放った飼い主の無責任な管理やマナーを批判する方がおられるが、僕は、果たしてそんな問題なのかな?と疑問を感じる。
たとえば、「振り込め詐欺」などと呼ばれる詐欺がある。そして、そんな犯罪に注意しまよう、とあれだけ叫ばれていても、騙されてしまう人が延々と存在する。
その程度のことでさえ周知できないのに、まして、ペットや外来の生き物を野に放した場合におきる問題のようなマニアックな事象を周知させることなどできるはずもなかろう。
飼い主が責任を持たないから問題がおきた、という発想は、机上の空論以外の何物でもないような気がしてならない。
問題は、生き物に限らず、欲しいと思えば遠く彼方のものでも手に入る現代人の生活スタイルにあるのではなかろうか?
しかし、貿易をやめ鎖国することなど現実的ではない。
ではどうしたらいいのか。
さて、原発は必要という人は、言い換えれば、今の暮らしを変えたくない人だと言える。
一方で、原発は不要という人にはいろいろな理由があるが、例えば、「原発なしでも、エネルギーは足りている」と主張する人は、言い換えるなら、「別に原発がなくても、今の暮らしを維持できるはず」と考える人になる。
それから、「原発をやめ、自然エネルギーに置き換えるべきだ」と主張する人もやはり、今の暮らしは変えたくない人。
そういう意味では、原発賛成の人も反対の人も、同じ意見だと言える。
だが原発問題の本質は、原発が必要になり兼ねないくらいの暮らしを、人が要求していることではないのだろうか?
もちろん自分も含めて、足ることを知らずに、新しい便利なアイテムに次々と飛びつき、小型のコンピューターまで持ち歩くような暮らしをしておきながら、原発反対などというのは、もしかたら、きわめて滑稽な話なのかもしれない。
僕が見聞きした範囲では、養老猛さんが新聞紙上の対談で、少々違った意見を伸べておられた。
「原発だけでなく、化石エネルギーもなくなればいい。それは困ったことではなくて、江戸時代の暮らしに戻るだけだ。」
と言った風なことを。
江戸自体の暮らしに戻れば、外来の生き物があちこちで爆発的に増えるなどということもあり得ないに違いない。
江戸時代の暮らしに戻れば、今の人口は維持できないだろうから、それで生きれる人だけが生きればいいということになるが、先日取り上げた、テレビでのムツゴロウさんの発言に相通じるものがある。
勇気ある発言だな、と思う。
自然や環境に関する問題は、人が何を捨てるかの問題。しかし、僕にはそれを言い切れるだけの勇気も根性もない。
そもそも、自然写真などという仕事は、豊かな経済の上に成り立つ仕事であり、途上国ではありえないだろう。もしかしたら僕などは、日本の経済的な豊かさの恩恵をもっとも受けている者の一人なのかもしれない。
いや、それでは誰も何も言えなくなるから、意見を言うということは、もしかしたら、自分のことを棚に上げた上で発言することなのかもしれない。
|
| |
2011.10.5(水) 食べ物
ここ数日で自分が食べたものを思い浮かべてみると、その中に、日本原産のものはほとんど含まれていない。
せいぜい、近海物の魚くらいではなかろうか。
牛だって鶏だって、ほとんどすべての野菜だって、たとえ国内で飼育や栽培されていたとしても、元々は外国の生き物だ。
一方で、そうして日本に食べ物として持ち込まれた生き物の中には、ウシガエルのように食べ物としては機能せず、さらに逃げ出して野生化し、日本固有の生き物を食べたりして日本の生態系に悪影響を与えると問題視されているものがいる。
ウシガエルの餌として日本に持ち込まれたアメリカザリガニなども、人の食べ物の餌なのだから、大きく分ければ、食糧として持ち込まれたものに分類できるだろう。
嫌われ者のブルーギルだって、最初に放流される際には、場合によっては食べ物になると考えられたようだ。
ありがたい食べ物と迷惑な外来の生き物が、実は紙一重。
いや紙一重というよりは、ワンセットであり、表と裏の関係といった方がいいのかもしれない。
日本に食用として持ち込まれた生き物が食べ物として機能するかどうは、やってみなければ分からないのであり、場合によっては食用になるが、場合によっては困った外来種になるのであって、困った外来種は、ありがたい食べ物を得るための犠牲のようなもの。
人間って勝手だなぁと思う。
外来の生き物は怪しからんと主張する人が、牛や鶏を美味い美味いと言って食べるのである。ウシガエル、アメリカザリガニ、怪しからんと主張する人は、外国の生き物は食べるべきではないのではなかろうか?
しかし、そんなことを書いている僕だって、ウシガエルやアメリカザリガニがいない方がいいと思う。
人間って、悲しいなと思うことがある。
|
| |
2011.10.4(火) 僕に求められたこと(後)
ムツゴロウさん、こと作家の畑正憲さんが、以前テレビの番組で、北海道でのヒグマと人の事故について、
「いいじゃないですか!ヒグマに人が殺されるって言っても、年に一人か二人でしょう?それくらいヒグマにも食べさせてあげなさいよ。」
と語るのを聞いた際には、金づちで頭を殴られたかのような衝撃を受けた。
過激な言葉、自然原理主義者の偏った発言に聞こえるかもしれないが、自然を大切にするというのは基本的にそんなことである。
そこに触れずに、
「自然を大切にしましょう。」
と言うのは、むしろ、口先だけの言葉。
ただ、誰もがそんな風にはっきりと物を言えるわけではない。
たとえば、政治家が同様の発言をしたなら、間違いなく袋叩きにあい、そのままの地位にとどまることはできないだろう。
でも作家なら、それを口にできるし、そこに作家の存在価値があるとも言える。
人間には、さまざまな立場がある。
学校の先生方の集まりに初めて参加した際に、僕が感じたことは、先生方の当たりの柔らかさだった。先生という立場も、政治家などと同様に、
「それくらいヒグマにも食べさせてあげなさいよ。」
などとは、口が裂けても言えない立場だと言える。
一方で僕は、はっきりものを言うタイプだから、講演を依頼された際に真っ先に考えたことは、そんな僕が、先生方の集まりに出かけることが、場違いではないかどうかだった。
ところが、先生方は決してはっきりした物言いを否定するわけではないし、むしろいろいろな立場の人からの意見を求めておられることがわかった。
そして、それに応えられないのなら、自分の存在価値がないのではなかろうかと感じた。
「水と地球の研究ノート」(全5巻・偕成社)は、小学校の教育現場を強く意識して作った本だが、製作中はすべてが手一杯で、どんな風に教育現場を意識するかまでは気が回らなかった。
だが出版後に、先生方の集会に参加させてもらった結果、意識するは意識するでも、先生方に同調するのではなく、僕らは、先生方の立場では触れにくい部分についても触れたり、補間するような本を目指さなければならないのではないかと感じた。
同調したり、支える本を否定するつもりは毛頭ないし、そんな本も必要なのだと思う。例えば、参考書である。
だが、もしも自分が作家として発信しようと思うのなら、自分なりの視点を打ち出さなければならないのだと。
|
| |
2011.10.1〜3(土〜月) 僕に求められたこと(前)
火山が噴火した際の溶岩は、やがて冷えて固まり、火成岩と呼ばれる岩になる。
その際に急激に冷えると、岩に規則的なひび割れが入る。兵庫県にある玄武洞などは、そのひび割れが実に見事な模様を呈し、理屈を知っていても、なんでこんな形に?としみじみ思う。
岩は、水や風の力で砕かれて砂になり、海に堆積して固まり、今度は堆積岩と呼ばれるタイプの岩になる。
そうした地球の出来事を、一冊の本にまとめてみたい。
先日、火山の撮影のついでに鹿児島県内の滝を幾つか回ってみたら、火成岩の岩場が多かった。さすがに火山の国・鹿児島だ。


さて、高校で地理を教えておられるH先生から、たいそうがっかりした表情で話しかけられたことがあった。以前にも、確か2〜3度書いたことがある。
「武田さん、今日は本当にがっかりさせられた。授業中に何か質問ある?って聞いたら、川の水はどこから来るんですか?なんていう初歩的な質問をする生徒がおるんよ。」
「ほうほう。」
「それでね、山に雨が降って、それが地下にしみこんで地下水になって湧水になって湧いてくるんやろうと説明したら、高校生にもなって、理解ができんっち言うんだからがっかりするよなぁ。」
「そうでしたか・・・。でも僕、その子の気持ち、わかるような気がします。」
「えっ!分かる?どんな気持ち?」
「僕は湧水を見たら、不思議やなって思うんです。」
「うん。」
「不思議やなってことは、それが自分の理解を超えていて分からないということでしょう?僕にとって本当によくわかることなら、不思議じゃなくて、当たり前って感じるはずなんですよ。」
「なるほど。」
「湧水を見て不思議だなって感じなかったら、僕はつまらないように思うのですが、学校教育って、理屈を覚えさせてそれでもって分かったと言わせたがる。でも、研究者になるような人なんかは、不思議だなって、つまり分からないって感じるからのめり込んでいくんですね。まあ、受験をする場合は、そこで分かったって思えた方が得をするのでしょうが・・・・」
「面白い!あんたに言うてみてよかった。そうか、そうか。そんな話が聞きたいんよね。」
そんな会話を、いずれ本の中で表してみたいものだと思った。
そんな思いを表現するために、人と意見交換をし、たくさんの指摘をしてもらい、試行錯誤してそれを乗り越え、一筋縄では表せないことを表現しようとすることは、僕の長年の夢でもある。
勉強することとは、自分が分かってないということを知ること。
そしてわからないからこそ面白いし、もしも人生から分からないもの、つまり不思議なものがなくなってしまったなら、大変に味気ないに違いない。
一言で面白いといってもいろいろな面白さがあるが、自然科学における面白さとは、そんなことだと僕は理解している。
ただ、それが果たして通用するのかどうか、僕には自信がなかった。H先生が、単なる変わり者なだけではないか?と。
さて、以前、学校の先生方の集会で講演をした際の感想文が昨晩届き、ざっと目を通してみたら、先生方が僕に求めたのは、やっぱり圧倒的にそこだった。
|
| |
先月の日記へ≫
|